
関節リウマチ(RA)は昔から人々を苦しめてきた病気ですが、その治療法は時代とともに大きく進歩してきました。ここでは、紀元前の古代から現代にいたる関節リウマチ治療の変遷を、一般の方向けにわかりやすく解説します。
目次(このページの目次)
古代〜19世紀:痛みを和らげる時代の関節リウマチ治療
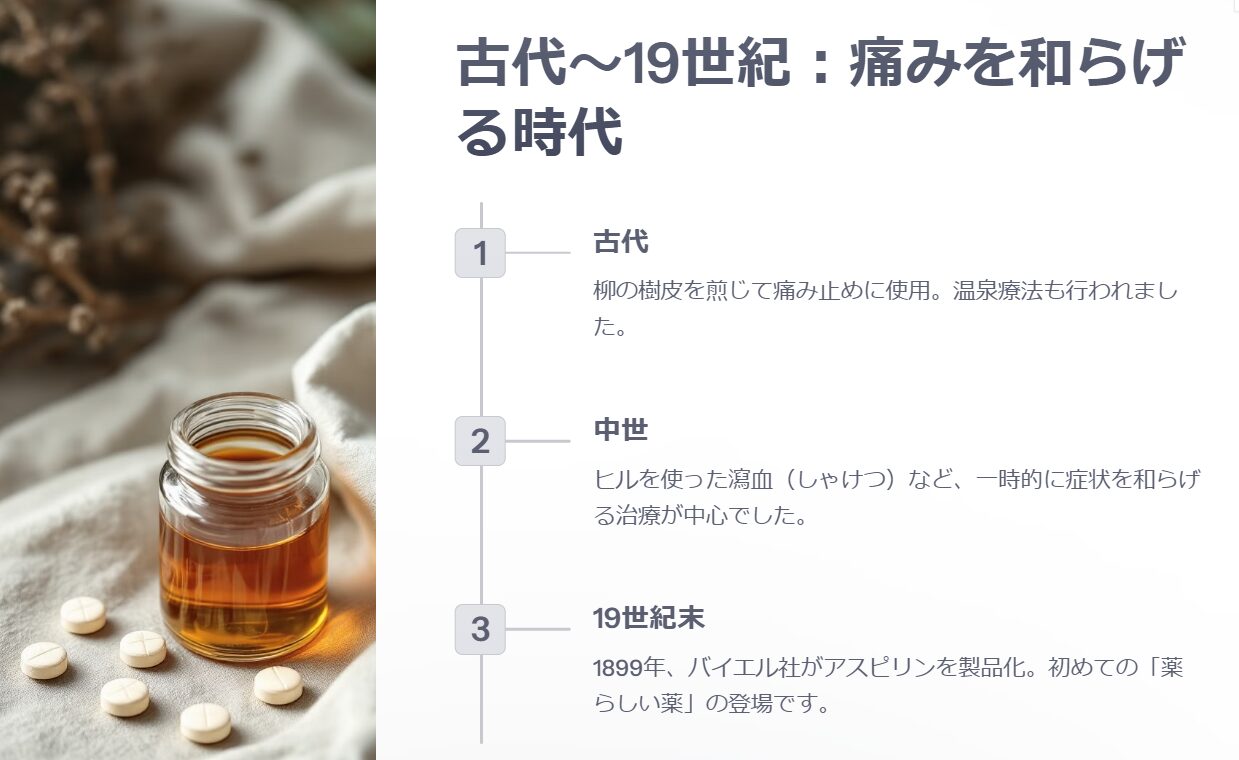
古代から中世にかけては、関節リウマチの正体は分からず、痛みをとる対症療法が中心でした。例えば古代ギリシャや中国では柳の樹皮(ヤナギの樹皮)を煎じて痛み止めに使っていたそうです。
柳の樹皮には後に「アスピリン」として知られる成分が含まれており、炎症や痛みを和らげる効果が古くから知られていたのです。また、温泉や温熱療法によって痛みを緩和しようとしたり、逆に冷水や氷で関節を冷やす療法も行われました。
中世ヨーロッパでは瀉血(しゃけつ)といって、患部から血を抜く治療(ヒルを使うなど)さえ行われました。これらは一時的に症状を和らげるだけで、病気自体を治すことはできませんでした。。
19世紀になると、痛み止めとしてサリチル酸が科学的に抽出されるようになります。柳の樹皮から得られたサリチル酸をもとに、1899年にドイツの製薬会社バイエルがアスピリンを製品化しました。これは副作用が比較的少ない解熱鎮痛薬で、関節リウマチの痛みを和らげる初めての「薬らしい薬」でしたが、痛みを止める対症療法であり、アスピリンでその場の痛みは和らいでも関節や骨の破壊進行を止めることはできませんでした。
効果的な根本治療が無かった時代、画家ルノワールは重度の関節変形に苦しみながらも包帯で筆を握りしめ制作を続けた記録が残っています。この頃のリウマチ治療は「痛みをとるだけ」の時代であったと言えます。

20世紀前半:新たな薬の模索と「金治療」
20世紀に入ると、医学界は関節リウマチを抑える特効薬を求めて様々な試行を始めます。アスピリンのような非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は引き続き使われましたが、痛みを和らげる以上の効果を持つ薬が望まれていました。
その中で注目されたのが「金(ゴールド)製剤」による治療です。1920〜30年代当時、一部の医師たちは関節リウマチを「関節の結核」のようなものではないかと考えました。結核治療に使われていた金の化合物が関節リウマチにも効くかもしれない、と期待されたのです。実際に関節リウマチ患者に金の注射を行う試みがなされ、一定の効果が認められたことから、「金治療」は長らくリウマチ治療の主流となりました。特に副作用に注意しながら筋肉注射で金製剤を投与する方法が、少なくとも30年間以上にわたって世界中で広く用いられたのです。
金治療以外にも、この時代には薬以外の療法(温熱療法や理学療法、食事療法など)も模索されました。しかし、いずれも関節リウマチそのものを治す決め手にはならず、症状の緩和が精一杯でした。こうした背景から、医学者たちは引き続き新しい治療薬を探し求めることになります。
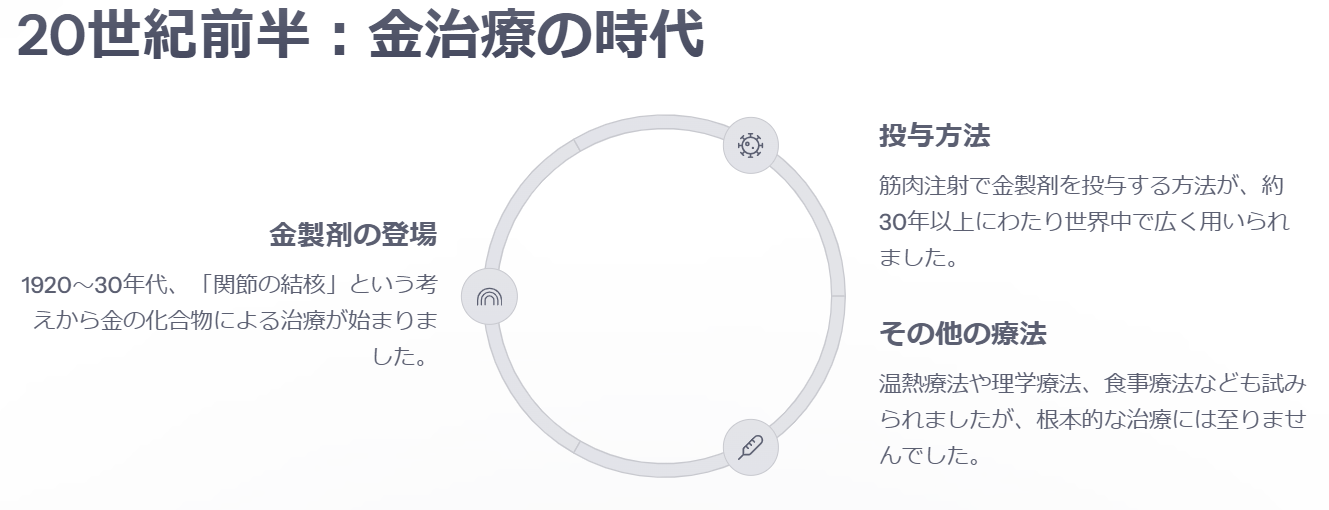
1940年代後半:ステロイドの登場と衝撃
1948年、リウマチ治療に革命的な薬が登場します。米国のヘンチ医師らによってステロイド(副腎皮質ホルモン剤)の効果が発見されたのです。ステロイドは体内の炎症を強力に抑える作用があり、関節リウマチの激しい痛みや腫れを劇的に和らげました。それまでのどの薬とも比較にならないほど炎症を抑える効果を示したため、当初は「夢の新薬」としてリウマチ治療の中心に躍り出ます。
実際、ステロイドを世界で初めてリウマチ患者に投与した功績により、ヘンチ医師は1950年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています。このようにステロイド剤の登場は当時の患者・医療者に大きな衝撃と希望を与えました。
しかし、ステロイドはあくまで炎症や痛みを抑える対症療法であり、長期連用すれば副作用も深刻になります。例えば骨粗しょう症や感染症、糖尿病の悪化など様々な副作用リスクがあるため、漫然と使い続けることはできません。また、ステロイドでは関節の破壊そのものを止めることはできないため、根本的な治療とは言えませんでした。
そのため医師たちはステロイドで症状を抑えつつ、さらに関節破壊の進行を食い止める新たな薬を模索し続けました。
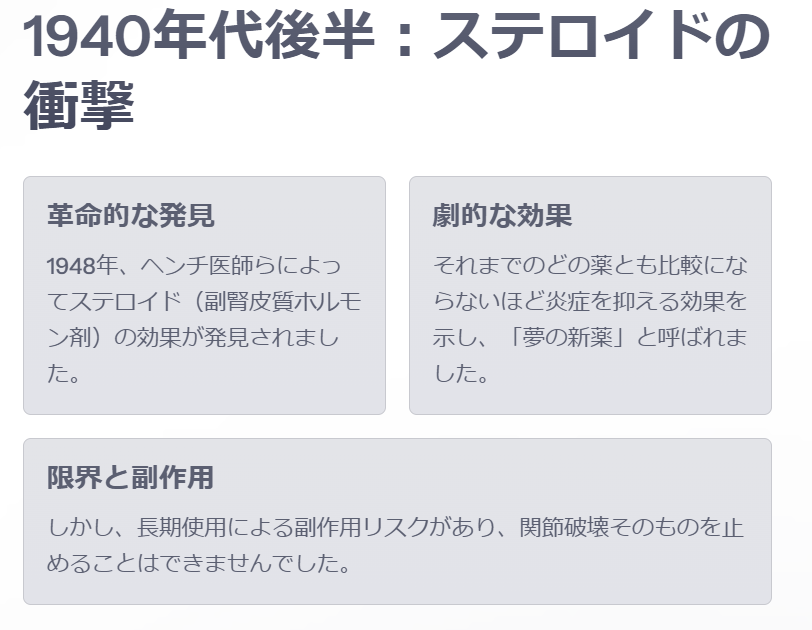
1950〜1980年代:抗リウマチ薬(DMARDs)の模索
ステロイド登場後の1950年代以降、リウマチの病勢そのものを抑える薬が求められ、様々な薬剤が試されました。こうした薬は「抗リウマチ薬」と総称され、現在では疾患修飾性抗リウマチ薬(DMARDs)とも呼ばれます。1950年代には抗マラリア薬(マラリアの薬)であるクロロキンが関節リウマチに有効かもしれないと報告され、炎症を和らげる目的で使われ始めました。
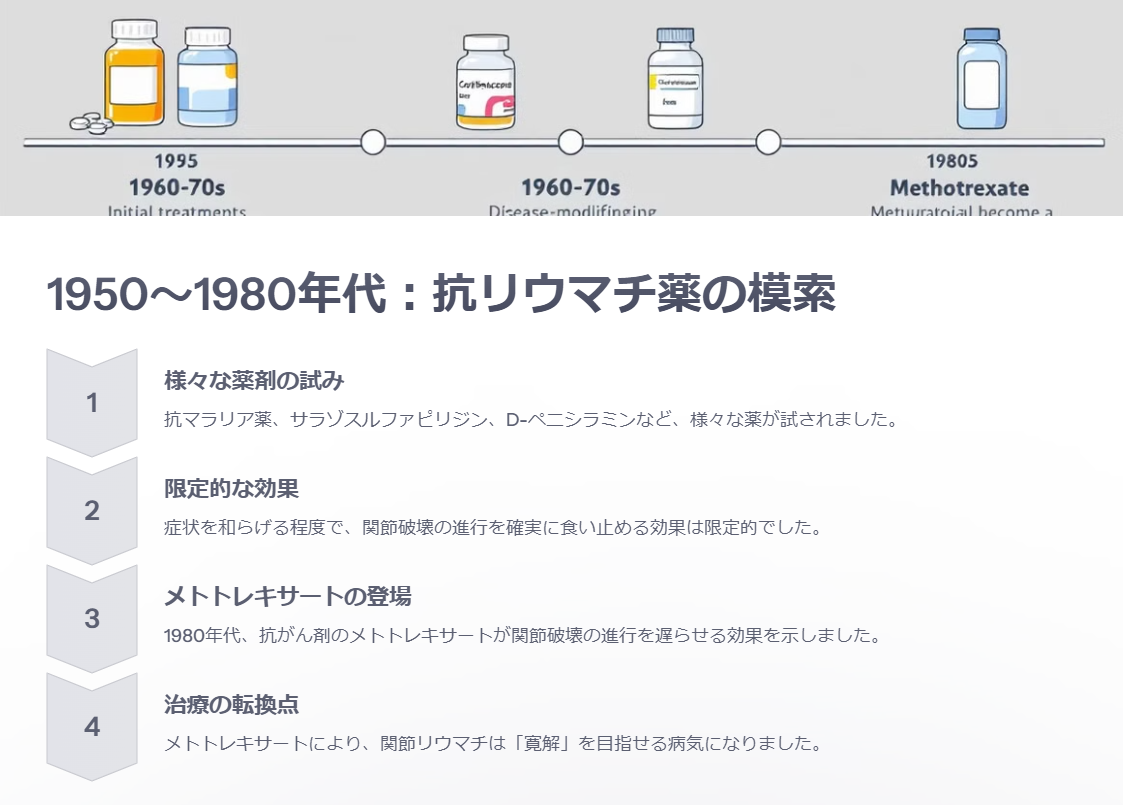
同じ頃、抗生物質由来のサラゾスルファピリジン(スルファサラジン)や、ペニシリンから派生したD-ペニシラミン、さらには免疫抑制剤のアザチオプリンなど、本来別の病気治療に使われていた薬が「リウマチにも効くかもしれない」と転用されました。
さらに、前述の金製剤治療も引き続き行われています。このように複数の薬剤が試みられましたが、いずれも症状を多少和らげる程度で、関節破壊の進行を確実に食い止める効果は限定的でした。
そうした中、1980年代に転機が訪れます。もともと抗がん剤として使われていたメトトレキサート(商品名リウマトレックス)が、関節リウマチにも大変有効であることが分かったのです。
メトトレキサートは葉酸代謝を阻害することで免疫の暴走を抑える薬ですが、関節の腫れや痛みを取るだけでなく、関節破壊の進行そのものを遅らせる効果が初めて確認されました。
メトトレキサートは1988年に米国でリウマチ治療薬として承認され、日本でも少し遅れて1999年に承認されました。現在でもメトトレキサートは関節リウマチ治療の第一選択薬(最初に使う基本薬)として広く使われており、多くの患者さんの病勢をコントロールする鍵となっています。
1990〜2000年代:生物学的製剤の登場
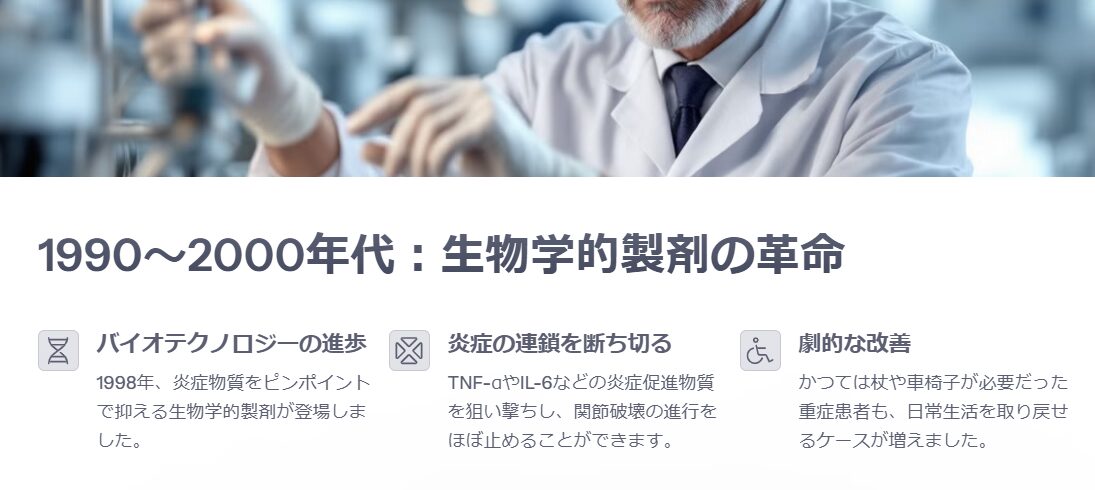
メトトレキサートによってリウマチ治療は大きく前進しましたが、効果が不十分な患者さんもいました。
1990年代後半になると、さらに新しいタイプの強力な薬が開発されます。1998年、関節リウマチの炎症悪化に関与するサイトカイン(細胞から分泌される炎症物質)をピンポイントで抑える初の治療薬が海外で登場しました。
これが生物学的製剤(バイオ製剤)と呼ばれる薬です。生物学的製剤とは、遺伝子組み換えなどバイオテクノロジーによって作られたタンパク質製剤で、体内の特定の炎症物質の働きを狙い撃ちします。
最初に登場した生物学的製剤はTNF-αという炎症促進物質(サイトカイン)を抑えるもので、これによって関節リウマチの炎症連鎖を断ち切ることが可能になりました。
その後も**インターロイキン-6(IL-6)というサイトカインを抑える薬や、免疫細胞そのものを標的とする薬など、次々に新たな生物学的製剤が開発されました。生物学的製剤は、関節の腫れや痛みを劇的に改善できるだけでなく、関節や骨の破壊進行をほぼ止めてしまう効果を持っています。
日本でも2003年に最初の生物学的製剤(インフリキシマブ=商品名レミケード)が承認され、以降複数の製剤が使えるようになりました。
生物学的製剤の登場によって、関節リウマチの予後(将来の見通し)は飛躍的に改善しました。かつては杖や車椅子が必要だったような重症患者さんが、生物学的製剤による治療で症状が落ち着き、日常生活を取り戻せるケースが増えたのです。
2010年代:JAK阻害薬という新しい飲み薬
21世紀に入り、生物学的製剤に続く新たな治療オプションとして登場したのがJAK阻害薬です。2010年代(2013年)になると、生物学的製剤と同様にサイトカインの働きを抑えることができる飲み薬が開発されました。JAK阻害薬は、細胞内のヤヌスキナーゼ(JAK)という酵素の働きをブロックすることで、サイトカインが引き起こす炎症シグナルを抑える薬剤です。生物学的製剤と同等かそれ以上の効果を発揮することもあります。
JAK阻害薬の大きな利点は経口薬(飲み薬)であることで、生物学的製剤は分子が大きなタンパク質なので点滴や皮下Injectionなど注射で投与する必要がありますが、JAK阻害薬は分子が小さいため錠剤やカプセルの形で服用できます。
現在の標準治療と近年の進歩
こうした薬物療法の飛躍的進歩により、関節リウマチ治療の目標は「症状を抑えること」から「病気自体を抑え込んで寛解(症状が出ない状態)に導くこと」へと大きく変化しました。
現在の標準的な治療戦略は、できるだけ早期にメトトレキサートで治療を開始し、効果が不十分な場合は生物学的製剤やJAK阻害薬を追加していくという方法です。

実際、十分な治療法が無かった時代には関節リウマチ患者さんの平均余命は一般より10年短いとも言われていましたが、現在では適切な治療によって寿命も健常人と遜色ないレベルにまで改善**し、関節の変形のために手術を受ける人も激減しています。
関節リウマチは、もはや「不治の病」や「寝たきりになる病気」ではなく、適切に治療すれば寛解を目指せる病気となったのです。
まとめ: 関節リウマチの治療は、古代の痛み止めに頼る時代から、20世紀中頃のステロイドによる炎症コントロール、そして後半の抗リウマチ薬による病勢抑制へと段階的に進化してきました。21世紀に入って生物学的製剤やJAK阻害薬が登場したことで、関節破壊を防ぎ寛解に導くことが可能となり、患者さんの生活の質や寿命は飛躍的に向上しています。
