目次
四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)の概要
- 定義・症状
四十肩・五十肩は肩関節周囲炎や凍結肩(癒着性関節包炎)とも呼ばれ、特に40~50歳代を中心に、肩関節の痛みや可動域の制限が徐々に進行する疾患です。典型的には肩の挙上や外転が困難となり、日常生活動作(洗髪、衣服の着脱など)に支障が出ます。 - 自然経過
一般的には数ヶ月~1~2年(凍結肩などでは場合によっては数年)かけて自然に回復するケースもありますが、痛みや可動域制限が長期間続くことにより、生活の質(QOL)の低下が問題となります。
2. 鍼灸治療の効果概説
近年、四十肩・五十肩の疼痛と可動域制限に対して、鍼灸治療が有効である可能性を示す研究が蓄積しています(1)(2)。鍼刺激により鎮痛物質(内因性オピオイドなど)の分泌や局所循環の改善が期待され、痛みの緩和と関節可動域の向上が得られると考えられています(2)。さらに、電気鍼(Electroacupuncture, EA)では、鍼に電気刺激を加えることで痛み抑制効果の増強が示唆されています(1)(3)。
3. 電気鍼による疼痛・可動域改善のエビデンス
3.1 メタアナリシス・系統的レビュー
- 電気鍼に特化した系統的レビュー
複数のランダム化比較試験(RCT)を統合したメタアナリシスによると、電気鍼は通常の手技鍼(マニュアル鍼)よりも、肩の痛み(VASスコア)および機能スコアの改善において優位性があると報告されています(1)。さらに、内服薬や理学療法などの従来治療に電気鍼を併用すると、従来治療のみよりも疼痛軽減効果が高いとの結果も示されています(1)。つまり、リハビリを受けながら鍼灸の併用を行うと疼痛改善がより増すという論文です。 - 鍼灸全般を対象とした系統的レビュー
鍼灸全般(電気鍼を含む)を対象としたレビューでは、短期~中期的に痛みの軽減と可動域の改善に寄与する可能性が高いとされています(2)。特に肩の屈曲可動域については改善効果を示す研究が多く、外転や外旋でも有益な可能性があるとする報告があります(2)。ただし、研究間のばらつき(サンプルサイズや研究デザインの品質の差)を理由に、エビデンスの質は「中~低」と評価されることが多い点にも留意が必要です(2)。
3.2 個別のランダム化比較試験(RCT)の知見
- 電気鍼 vs シャム鍼(プラセボ) + リハビリ
単盲検RCTでは、電気鍼群がプラセボ鍼群に比べて早期に疼痛が軽減したと報告されています(3)。治療開始から数週間以内にVASスコアが有意に低下し、可動域(特に前方挙上や外転)にも差が認められました。一方、6ヶ月後など長期の追跡では、機能スコアに大きな有意差がない研究もあり、早期効果は大きいが長期的には必ずしも差が維持されない場合があるとされています(3)。 - 電気鍼+運動療法 vs 運動療法のみ
中国を中心としたRCTでは、運動療法に電気鍼を組み合わせたグループが、運動療法のみのグループよりも疼痛と可動域の改善が有意に大きい結果が報告されています(4)。また、電気鍼は単なる鍼治療よりも鎮痛効果の発現が早く、症状改善までの期間を短縮できる可能性が示唆されています(1)(3)(4)。
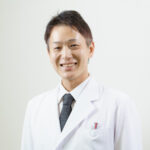 医師 高杉
医師 高杉鍼灸が、痛みや可動域を早く改善させるという報告が増えてきています。
4. 穿刺部位と施術方法
4.1 主な経穴
四十肩・五十肩に対して頻用される経穴は、肩関節周囲の局所穴および遠隔穴が挙げられます(2)(4)。
- 肩髃 (けんぐう, LI15)
- 肩髎 (けんりょう, TB14)
- 肩貞 (けんてい, SI9)
- 臂臑 (ひじゅ, LI14)
- 曲池 (きょくち, LI11)
- 合谷 (ごうこく, LI4) など
電気鍼の場合は、これらの経穴に刺鍼後、低周波や中周波など(例:2~100Hz程度)の通電を行い、数十分持続させる方法が用いられます(1)(3)。
4.2 施術頻度と期間
RCTや臨床報告では、週2~3回程度の施術を数週間から数ヶ月継続するプロトコルが一般的です(3)(4)。
- 例:6~8週間で合計12~16回の治療
- その後、必要に応じてメンテナンス目的の施術を行うケースもみられます。
5. 改善期間と安全性
- 改善期間
多くの研究では、治療開始から2~4週間程度で疼痛軽減や可動域の拡大が出始めると報告されています(3)(4)。6ヶ月以上の長期追跡では、プラセボ群や他の保存療法群との差が縮小する傾向も報告される一方、早期の症状緩和や機能向上を目的とする際には有用性が高いと考えられます(3)(4)。 - 安全性
鍼灸治療は、適切な方法で行われれば重篤な副作用のリスクが低いとされます。電気鍼においても、施術部位の軽度の出血や皮下出血、電気刺激による軽い不快感などが生じることはあるものの、深刻な合併症の報告は少ないとされています(1)(2)。
6. 結論
- 四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)に対する鍼灸治療は、痛みの軽減と可動域の改善に一定の有効性が示唆されています(1)(2)。
- 特に電気鍼は、通常の鍼治療よりもより早期に鎮痛効果が現れやすい可能性があり、運動療法や内服療法に加えることで相乗効果が期待されます(1)(3)(4)。
- 治療の頻度や期間は週2~3回を数週間続けるケースが多く、早ければ2~4週間で効果を感じる患者も少なくありません(3)(4)。
- 鍼灸治療、電気鍼ともに大きな副作用はまれであり、安全性は高いと考えられます(1)(2)。
- ただし、エビデンスの質(研究デザイン・サンプルサイズのばらつきなど)には限界があるため、今後は大規模かつ長期的なRCTやフォローアップ研究の蓄積が望まれています(2)。
参考文献
- Qi L, Tang G, Fu W, et al. Effects of electroacupuncture on pain and shoulder function in patients with adhesive capsulitis: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Pain Res. 2022;15:208–220.
- Sun X, Li Y, Wu J, et al. Acupuncture for frozen shoulder (adhesive capsulitis): A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Evid Based Complement Alternat Med. 2020;2020:1–12.
- Lo SF, Wu CH, Lin X, et al. Early pain relief and improved range of motion following electroacupuncture for frozen shoulder: A single-blind randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2020;34(7):354–368.
- Chen Y, Xu X, Xie D, et al. Effectiveness of electroacupuncture combined with exercise therapy for the treatment of adhesive capsulitis: A randomized controlled trial. J Tradit Chin Med. 2019;39(5):77–83.
鍼灸の様々な効果やエビデンスを知りたい方は、鍼灸ナビゲーションで探してみてください。
