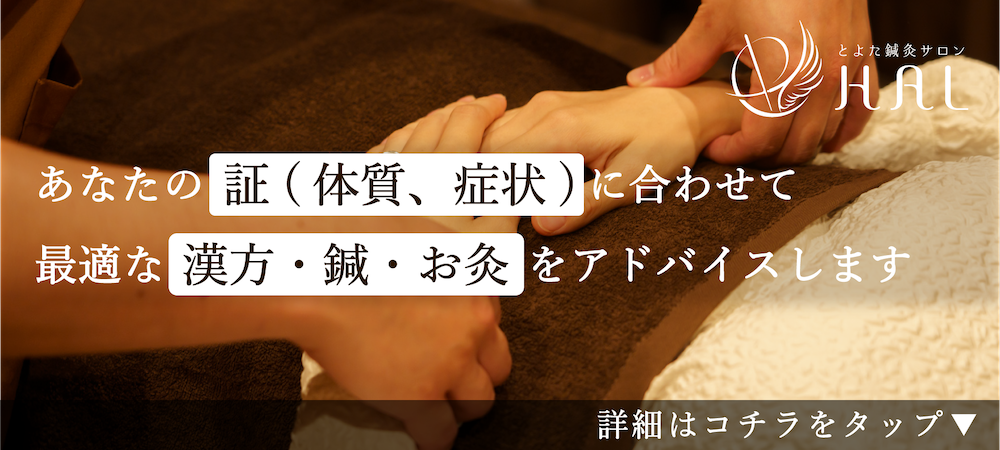「陳皮」(ちんぴ)
みかんの皮の部分を乾燥させたものです。自宅で作る事も可能です。食味は苦・甘で、食性は温性です。成分としてペクチン・クエン酸・ビタミンB1などが含まれ胃液の分泌を促し胃腸の働きを高めます。痰を取る作用。しゃっくりや嘔吐を鎮めまてくれる働きもあります。薬膳として食べる場合には、水につけて戻しサラダや煮物に利用する他、お茶や薬酒にも使います。
「ヨクイニン」
ハトムギの種の皮を除いたものです。食味は甘・淡で食性は涼性です。便秘・利尿・消炎・むくみ・肌荒れ・いぼ・身体の痛み・リウマチなどに使います。粉末にしてケーキやハンバーグなどに混ぜたり。粥に入れるなどして利用します。
「紅花」(こうか)
菊科紅花の花を乾燥させた物で、食味は辛で身体を温めます。冷え症や生理不順、更年期障害など女性特有の作用に用い、血液浄化・活性酸素除去などに使用します。料理の最後に花を散らすなどして食べます。
「銀耳」(ぎんじ)
銀耳とは、白きくらげのことです。食味は甘で食性は平性です。便秘の特効薬として使うほか、咳、のどの痛み、胸の痛み、生理不順、肌荒れに用いられます。滋養強壮作用もあります。薬膳としては、水につけて戻し、炒め物や煮物にするほか、ゆでてデザートにも使うことができます。
「金針菜」(きんしんさい)
ゆり科のホンカンゾウのつぼみを乾燥させたもので、食味は甘・辛で食性は平性です。利尿・血液の浄化作用があり、貧血や精神安定に用いられます。食材の栄養素としては鉄分はホウレンソウの10倍あり、食物繊維も豊富です。金針菜の食べ方は水につけて戻し、炒め物、和え物、煮物に使います。味は癖が無く、いろいろと使える食材です。
「サンザシ」
バラ科の実で、食味は酸・甘で食性は平~微温です。消化を助け、鎮痛、抗菌、強心作用、があります。また血圧を下げ、脂肪を分解して肥満対策にも用いられます。粉末をパンやケーキなどの素材に練りこみ、煮汁やスープに溶かし込んで使います。
「蜂花粉」(はちかふん)
花の花粉によっていくつかの種類があります。食味は甘で食性は平性です。滋養強壮、解熱作用があり、たんぱく質、アミノ酸、ビタミン、ミネラル、核酸などを含む。料理の仕上げに振りかけ、ヨーグルトにトッピングして食べます。
「百合」(ゆり)
百合根の乾燥したもので、食味は甘、食性は平性です。ビタミンB1、C、などの栄養があり、咳止め、強壮作用、利尿作用として用いられ、またストレスを弱めるとされています。炒め物やみそ汁の具材にしたり、ジャムにして使用します。
「竜眼肉」(りゅうがんにく)
竜眼の果実を乾燥させたもの、食味は甘で、食性は平性です。鎮静作用、滋養強壮作用があり、貧血、健忘症、不眠症に使われます。カリウムや食物繊維も豊富です。炒め物、煮込み、スープに入れたり、酒に漬けて戻して和え物やお菓子に使うほか、お茶や薬酒にも使われます。
「金銀花」(きんぎんか)
スイカズラの花で、葉や茎はニントウと呼ばれます。食味は甘で食性は涼性です。利尿・解熱・解毒・殺菌作用があり風邪の熱さましや関節炎などに用いられます。ティーパックに入れて煮込みみそ汁、カレーなどに加え使用されます。煮だした汁でドレッシングやたれとしても活用できます。
「松の実」
チョウセンゴヨウの種、食味は甘で食性は温性。滋養強壮、空咳、頭痛、便秘などに用いられます。食材としてビタミンB群やEも豊富です。良く炒ってトッピングに用います。
「黒米」
インディカ系の原生稲のもち米、カルシウム、鉄分、アミノ酸、ビタミン、ミネラルが含まれ、血液の浄化作用がある。妊産婦の体力の回復、ダイエットなどに用います。アントシアニンにより老化防止、視力の改善の目的に使われます。水につけ白米に混ぜて炊きます。
「何首烏」(かしゅう)
ツルどくだみの根で、食味は苦・甘で食性は温性です。白髪や腰・ひじの痛みや肝臓の強化に良い。酒に漬けこみ、強壮酒や家庭薬に使われます。ティーバックに入れて煮込みやみそ汁などに入れたり、エキスをたれとして使用する場合もあります。
「大棗」(ナツメ)
ナツメの実、食味は甘、食性は平から温性です。滋養強壮効果に優れ、補血作用、利尿作用があり精神安定にも良いと薬膳では考えられています。煮物、ご飯、鍋、などに加えます。お茶として飲まれることもあります。
「杜仲」(とちゅ・とちゅう)
杜仲の樹皮を乾燥させたもの、食味は甘、食性は温性です。古くから強壮・鎮痛剤として重宝されている。高血圧や関節痛にも用いられます。ティーバックに入れて煮込み、お茶などに使います(杜仲茶)
「髪菜」(はっさい)
砂漠地帯に生息する水苔の乾燥品、食味は甘、食性は寒性です。解熱・去痰・利尿作用を期待して使用されまた、抗ウイルス作用も薬膳では期待されています。。水につけて戻し、みそ汁・炒め物和え物などに使います。
「五味子」(ごみし)
チョウセンゴミシの果実で味は酸味があります。食性は温性で、身体を温める性格があり、滋養・強壮作用があります。気管支炎・喘息などで痰の多い咳の時に、咳止めの効果を期待し使用されます。
「菊花」(きくか)
菊の花の部分、味は甘く食性は平性です。解熱・頭痛鎮静作用・血圧降下のために使用され、動脈硬化や高コレステロール性に良いと考えられています。目の疲れや充血など目の症状にも用いられます。熱湯でさっとゆで食事に加えたり、お茶にして飲みます
「緑豆」(りょくとう)
豆もやしや中国春雨の原料になります。味は甘く食性は涼性です。清熱・解毒・利水作用があり、喉の渇きや・むくみ・ダイエット・熱性の風邪などの時に使われます。水で豆を戻して煮ものに使ったり、お茶として飲みます
「クコ子」(くこし)
クコの果実。食味は辛で食性は平性です。強壮剤として疲労や無気力・頭痛・目の疲れに用いられます。成分としてビタミンやミネラルの成分を含み、肝機能を高めてくれると考えられています。炒め物など料理に使ったり。酒に漬けて薬酒として飲んだり、菓子などに使います。