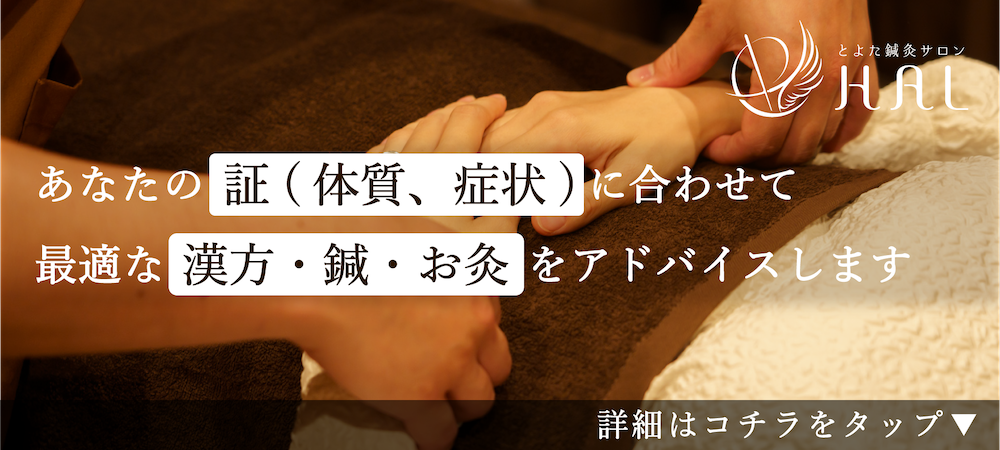薬膳は薬(体にとって働きをもつ)の意味をもつ膳です。薬として意味を持てるよう、漢方薬と同じように一定の原則に沿って、治療になるように作られています。
1つめの原則は良い状態に整えるための薬膳の考え方です。良い状態とは、体にとって不足がなく、邪魔なものがない状態を指しています。良い状態に保つための方法として、補虚(ほきょ)、瀉実(しゃじつ)、調和(ちょうわ)という3つの方法です。
まずは、この補虚(ほきょ)、瀉実(しゃじつ)、調和(ちょうわ)を紹介します。
補虚(ほきょ)とは足りない物を補うこと
補虚(ほきょ)とは、虚弱な体質を補う事です。30歳以上になると男女とも身体の機能が衰えてきます。衰えてきた状態を「虚」と表します。それを補うための食事が必要になり、これを補虚(ほきょ)と呼びます。
補虚(ほきょ)の発想は、足し算(プラスを加えること)です。何かを加えるという向きを、補と呼びます(補充とか、補足などという言葉で、補という言葉が使われるのと同じイメージを持ってください)。つまり補虚とは、体がマイナスの状態にあるときに、薬膳により何かをプラスして、体の中の状態を整える向きを指します。
体が熱を持ち悪い状態には、体の熱を取る働きを期待します。そのため、寒涼性の食べ物(アワ、トマト、キュウリ、スイカ、リンゴ、ナシ、カモ肉など)を使って身体の熱を取る、清補法という方法があり、これには滋陰(冷やす)の作用があります。
逆に体が冷えているときには、温性の食べ物(もち米、くるみ、鶏肉、アユ、スズキ、海老、黄耆、大ナツメなど)を使って身体を温める方法があり、温補法と呼びます。これには補気(臓器の状態を整える)、助陽(温める)の作用があります。
熱性の食べ物(くるみ、羊肉、肉桂、トウガラシ、さんしょう、こしょうなど)を使ってより急速に体を温める峻補法という方法もあります。
補虚(ほきょ)の視点から見た、風邪の対する薬膳
風邪はエネルギー不足している状態、すなわち「気虚」の時罹りやすくなります。そのため、免疫力を付ける食べ物でまず予防をします。粘膜を強くする「にら」や、「人参」、免疫力を高める魚介類、豆類、腸の活動を整えるヨーグルトや食物繊維などを取るのが有効です。
風邪のひきはじめには消化の良い糖分を中心に身体を温めるおかゆがおすすめです。かぼちゃやナツメを鶏がらスープで炊いたおかゆはほんのり甘く、口当たりが良いので食欲が無い時も食べやすいでしょう。
大根ゼリーの黒蜜掛け、寒天におろした大根・砂糖レモン洋酒で香り付けし寒天を煮どかす。それにナツメのエキスを加えた黒糖のシロップをかけて食す。喉の痛みを取り身体を温めるゼリーです。
瀉実(しゃじつ)は体にたまった悪いもの(邪)を取り除くもの
瀉実は邪気を取り除く(瀉)と言う意味で去邪とも言います。
邪気が入る事によって熱が出たり、頭痛がしたりなど病気の初めの実証の症状に対して行います。
加齢によって新陳代謝が落ちて、余分な水分や脂肪が体内で処理しきれずに滞ってしまう事が多い場合には、新陳代謝を促す食べ物で積極的に排出を心がける必要があります。
身体に水分が溜まっている人は血行も悪く冷え症になったり、便秘にもなりがちなので身体を温め、利尿作用のある食材が大切です。また脂肪がたまってしまう場合には、排出のために胃腸に優しく働きかける雑穀やきのこ、豆類がすすめられます。
体にたまってしまった水分を取り除くための方法として、雑穀を用いた薬膳があります。雑穀では玄米(発芽玄米)ハトムギなどが水分の代謝を良くしてくれます。
きのこも血中の脂肪を減らし毒素を体外に排出してくれます。豆類はホルモンバランスを整え、利尿作用を高め水分の代謝を促進してくれます。
瀉実(しゃじつ)を使用したタイプ別の薬膳例
気・血・水(津液)に滞りがある、代謝に障害がある人の薬膳例を紹介します。
1、気が滞る体質の方、つまり気の巡りが悪くなって滞うことから、太り気味で顔色が悪く、イライラや精神的に落ち込むことが多く、食欲不振、月経前症候群などに悩まされがちな方。こういった方の体質に合う食材は温性、辛味、苦味、酸味をもつ薬膳がおすすめです。気の巡りをよくして、うつ気分を発散(行気解鬱と言います)させて取り除きましょう。
2、血が滞る(お血)体質。これは血が滞って顔色が暗く、目の下にクマが出来る。肌は乾燥気味で便が黒く舌は紫色で暗いタイプの方です。この体質に合う食材は温性、辛味です。お血を取り去り、血を活き活きとめぐらせる(活血化)と良いです。苦味(ニガウリなど)は避け、寒涼性の食材は控えましょう。
3、水(津液)の流れが滞り痰湿が溜まっている体質 つまり肥満でむくみがあり、顔色は黄色っぽい。痰がで疲れやすく、眠気や体のだるさがある。 この体質に合う食材は平性、温性、辛味、苦味、淡味です。身体の湿や痰を取り除く(燥湿化痰)と良いでしょう。
4、身体が強く内臓機能が高ぶっている、陽盛体質。すなわち赤ら顔で声は大きく高い、呼吸が荒い。喉が渇き汗をかきやすく食欲旺盛である方です。 この体質に合う食材は涼性、寒性、苦味、甘みです。寒涼性の食べ物で熱を下げ、火熱症状を弱めると良いでしょう。
調和(ちょうわ)は体のバランスを整える方法
調和は季節によって身体の陰陽のバランスを整え、内臓や気・血・水を調和させる方法があります。
薬膳で生活習慣病予防の例
「高脂血症の予防」
コレステロールや中性脂肪が気になる人は、体内の余分な脂質を取り除くことが大事です。野菜・海草・植物繊維・お茶など排出効果の高い食品を取り入れながら体重をコントロールするとよいでしょう。
高脂血症となってしまう方は、まず老廃物を出す効果の高い食べ物を食事の最初に取る事から始めます。なぜなら、代謝が落ちてくるとエネルギーへの転換が十分に行われなくなり、その結果体脂肪や中性脂肪として老廃物が溜まり始めるからです。
そして、血中の中性脂肪と言う形で溜められてしまうと、エネルギーとして使われにくくなるばかりでなく排出もされにくくなってしまいます。野菜・海草・植物繊維・お茶など排出効果の高い食品を選ぶことで、この老廃物を体の外に出すことができるようになります。またキノコ類ネギやホウレンソウなど「活血」作用を持つものと組み合わせ主食より先に取るのが効果的です。
「夜遅くに食べる人の肥満防止」
夜型の生活になると夕飯の時間が遅くなり寝しなの食べすぎが肥満の原因になったりします。夕飯が遅い時には、香りの強い野菜を取り入れることで、滞っている「気」を巡らせて食べるスピードを抑制してくれます。
「肥満には健胃野菜を」
不摂生な生活を続けてきた人は、加齢とともに肥満・食欲不振・胃のむかつきなどの症状が現れやすくなります。胃腸病予備軍になる前に白菜やキャベツ・大根などの胃に優しい野菜を取る事で胃腸を休ませることが大切です。
「お酒を飲む人には瓜系がお勧め」
肝機能に問題がある人には肝臓をいたわる食生活も大切です。白菜や大根などあっさりした野菜や湯豆腐、煮豆などは肝臓に優しい食事です。二日酔いにはキュウリやズッキーニ・冬瓜などの野菜が解毒作用を持ち、お勧めです。
「冷え症には果物も常温で」
冷え症の人は普段の食生活も温めて食べる工夫をしましょう。身体を冷やす夏野菜やフルーツは温めたり常温にして食べましょう。煮炊きしたものを食生活の中心に据えます。
補虚(ほきょ)、瀉実(しゃじつ)、調和(ちょうわ)は、バランスをとり良い状態を保つ、というための方法です。今の状態をみて、補ってあげるのか、溜まってしまったものを排出するべきなのか、という視点で考えると薬膳の初心者でも、良い食事をとることができます。