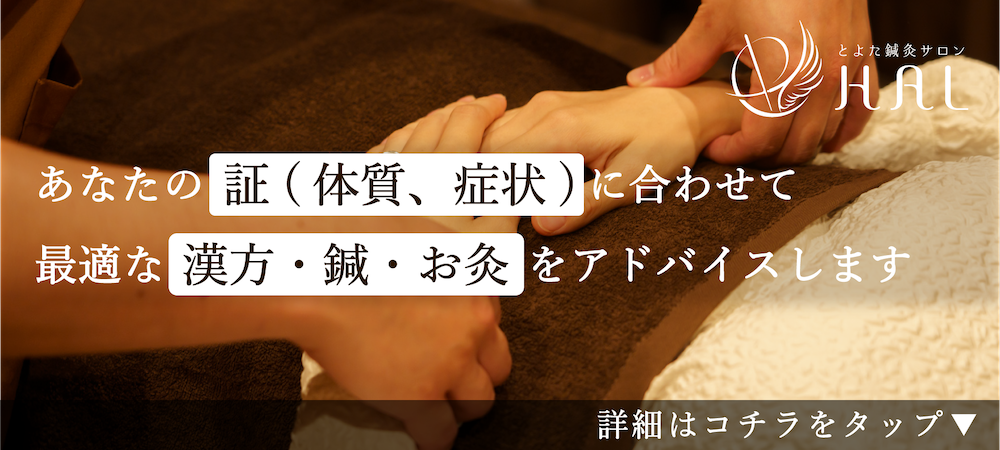慢性疲労症候群は、説明のできないだるさ、落ち込む感じ、睡眠障害や、考えがまとまらない、いろいろな自律神経症状が出るなど、なった人は周りに理解してもらえないつらさで悩む病気です。
このページでは、その診断基準の解説をします。気になる方、気になる方がいる方は、当てはまるかどうか見てみてください。
ちなみに、周りが理解してくれない原因の一つに、名前が悪い(慢性疲労症候群という名前が、疾患というより疲れだけを指すようなイメージでとられてしまう)という負の側面があり、実際に他国でも、Chroninc fatigue snydrome(慢性疲労症候群)の名称を、systemic exertion intolerance disease(SEID)という名前(全身性労作不耐性疾患)という病名に生まれ変わってこようとしていますが、まだ議論中でして、なかなか浸透していません。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK274235/?report=printable
慢性疲労症候群/全身性労作不耐性疾患の診断基準
1.症状の発症前に可能であった職業、教育、社会、個人における活動が不能または相当に傷害されている状態(Substantial reduction of impairment)が6ヶ月以上持続している。極度な疲労を伴わない
2.活動後の倦怠感がある(Post-exertional malaise)
3.睡眠による爽快感が得られない(unrefresing sleep)
また次のうち1つを満たす
1.認知機能障害(Cognitive impairment)
2.立位の不耐症(Orthostatic intolerance)
これが最も新しい診断基準になります。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK274235/
また、日本のAMEDという治療方法を考える研究の助成団体では、線維筋痛症に対し、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)臨床診断基準(案)を出しています。
筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)臨床診断基準(案)
Ⅰ.6ヵ月以上持続ないし再発を繰り返す以下の所見を認める
(医師が判断し、診断に用いた評価期間の50%以上で認めること)1. 強い倦怠感を伴う日常活動能力の低下*
2. 活動後の強い疲労・倦怠感**
3. 睡眠障害、熟睡感のない睡眠
4. 下記の(ア)または(イ)
(ア)認知機能の障害
(イ)起立性調節障害Ⅱ.別表1-1に記載されている最低限の検査を実施し、別表1-2に記載された疾病を鑑別する (別表1-3に記載された疾病・病態は共存として認める)
1994年の福田クライテリアによる慢性疲労症候群の診断基準
6か月以上にわたり次のうちの4つ以上の症状を認める
•–記銘力の障害または集中力の障害
•–咽頭痛
•–頚部または腋窩のリンパ節の圧痛
•–筋肉痛
•–多関節痛
•–新規発症の頭痛
•–睡眠による爽快感の欠如
•–労作後の倦怠感
いくつかの診断基準を解説しました。
これらのような基準を作り、日本の場合には慢性疲労症候群と間違えやすい他の病気を除外した上で、診断しようとしています。この病気に実際になっている人たちを、しっかり集め、解決方法が研究されています。なんとも言えない症状で漢方薬外来に来られる方も多いため、漢方薬を扱う医療者も、この疾患を捉えて、今後の動向に注目する必要があります。
なぜ診断基準が必要か、というと、慢性疲労症候群は、様々な状態を呈することがあり、国によってはDisease of thousand names(1000の名前を持つような様々な症状)がでる、一連の状態を指すとされ、日本では約36万人が存在する(人口の約0.3%)と推定されているものの病気の概念やその患者さんたちの症状は様々なので、解決のためには一つの同じ集団として解決方法を探っていこうという目標のために必要だからです。
実際には、ホルモンの異常所見(副腎ホルモンの分泌量低下)や、免疫性のサイトカインが正常な方と異なっており、何らかの病態の関与がある、実際の病気であると専門家は考えており、解決にむけた研究が行われています。